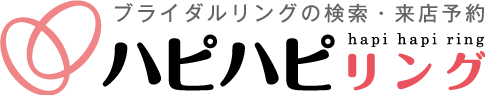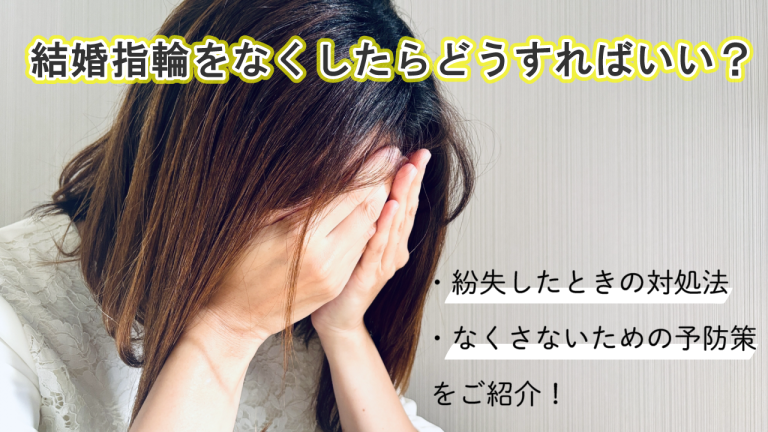大切な結婚指輪をなくしてしまったらショックですよね。「夫婦の想いが詰まった結婚指輪をなくすなんて・・」と困惑するかもしれませんが、まずは慌てずにできることから対処していきましょう。
この記事では結婚指輪をなくしてしまった場合の対処方法やなくさないための予防方法をご紹介します。
結婚指輪をなくした際の対処法
結婚指輪をなくしたときの対処法は4つ。
・心当たりがある所を探す
・警察署や施設へ問い合わせする
・購入したブランドの保証内容を確認する
・パートナーに報告する
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
きっと見つかる!落ち着いて心当たりがある所を探す
結婚指輪をなくしてしまったらまずは落ち着いて心当たりがある場所から探していきましょう。
ここでは、家の中でなくしやすい場所と外出先でなくしやすい場所をそれぞれご紹介します。なくしてしまった方のエピソードも合わせてご紹介しますので、指輪を探す際のヒントにしてください。
家の中でなくしやすい場所
・キッチン
・お風呂
・洗面所
・トイレ
・寝室の枕元
・キッチンや浴室の排水口
・エプロンや部屋着のポケット
家の中で結婚指輪をなくしてしまった人のエピソード
“結婚指輪をなくして探して10日間 ようやく見つけて一安心… 大掃除の末、絵本の隙間から無事発見!” / X(旧Twitterより)
“早くも結婚指輪をなくしたかもしれないと今朝思ってから丸一日震えて過ごしましたが、無事一昨日着ていたスラックスのポケットから出てきました 本当によかった、まじで焦った” / X(旧Twitterより)
”なくした結婚指輪みつかった サーキュレーターの中から出てきた なぜ” / X(旧Twitterより)
絵本の隙間やサーキュレーターの中など、思いがけない場所から見つかることもあるんですね…!「こんなところにはあるはずがない」という場所も諦めずに探したら見つかる可能性がありますね。
外出先でなくしやすい場所
・職場の更衣室
・病院の更衣室
・商業施設や駅のトイレ
・海やプールなどのレジャー施設
外出先で結婚指輪をなくしてしまった人のエピソード
”結婚指輪をなくした夫、さっきまでいたジムに戻って無事に見つけたそうです。とりあえずよかった。” / X(旧Twitterより)
”昨年春頃に紛失した結婚指輪が出てきました クリーニングにだした礼服から ちなみに新しい指輪は再来週くらいに出来上がる予定です…” / X(旧Twitterより)
”実は昨日、結婚指輪を無くしたと大騒ぎしていたのですが、一昨日のMRIで外してそのままにしていただけでした” / X(旧Twitterより)
外出先では、手を洗ったときに外してポケットに入れっぱなしにしたり、その場のおける場所に一時的に置いたりして失くしてしまうことが多いようです。心当たりがある場所を探してみてくださいね。
外出先でなくした場合は警察署や施設へ問い合わせする
警察署や施設への問い合わせ
結婚指輪を紛失してしまったら、まずは迅速に警察署やその日利用した施設の窓口に連絡をしましょう。
これにより、万が一誰かが拾って届けてくれている場合、すぐに対応が可能になります。
公共交通機関などを利用した際に指輪を紛失した場合、その施設の遺失物担当窓口や最寄りの警察署に問い合わせてみてください。また、問い合わせ時には結婚指輪の特徴を具体的に伝えることで、見つかる確率を高めることができます。
遺失物届の提出
指輪を紛失したことに気づいたらできるだけ早く、警察に「遺失物届」の提出をしましょう。どこの警察署でも構いませんが、紛失した場所の目途が立っている場合はその地域を管轄している警察署または交番へ提出するのがベスト。
遺失物届を提出するために必要な情報は、
・指輪の特徴(色/刻印/形など)
・失くした日時や場所
・利用した施設や交通機関
遺失物届はオンラインでも届出可能(※地域による)ですが、受理されるまで時間がかかってしまうので、早く見つけるためには警察署や交番に直接行くのがよさそうです。
【リンク:警察署 落とし物の届出・検索】
購入したブランドの保証内容を確認する
ひと通り探しても見つからない場合は、購入したブランドや店舗の保証内容を確認してみましょう。
以下の方法で確認を行います。
・購入時の保証書を確認
結婚指輪を購入した際に同封されている保証書に記載の内容を確認してみましょう。公式HPでも確認はできますが、購入した当時と内容が変わっていて該当しない場合もありますので注意が必要です。
・直接店舗へ問い合わせ
ブランドやショップによっては、紛失保証がついている場合があります。お店の負担が大きくなるので無償で同じものを…というわけにはいきませんが、同じデザインの結婚指輪を割引価格で購入できる保証サービスもあるようです。まずは購入店舗に問い合わせをしてみましょう。
早めにパートナーに報告する
結婚指輪をなくした場合、正直にパートナーに報告することが最善の行動です。
ふたりの想いが詰まった結婚指輪をなくしてしまい、パートナーに対して罪悪感が湧くかもしれませんが、結婚指輪をしていないことに気づきパートナーを不安な気持ちにさせてしまう可能性もあります。早く見つけるためにも自分からパートナーに報告しましょう。
また、このような状況でお互いにサポートすることにより、絆を再確認する機会にもなるでしょう。パートナーに伝える際は、正直な気持ちを伝え、冷静に事実を話すことが大切です。
結婚指輪をなくさないための予防策
結婚指輪をなくさないための予防策は4つ。
・なるべく外さないようにする
・外した時の保管場所を決めておく
・外出時はジュエリーポーチや専用ケースを活用する
・サイズが緩くなったらメンテナンスに出す
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
なるべく外さないようにする
結婚指輪をなるべく外さないようにするのも、指輪を失くさない予防策のひとつ。特に洗面所の鏡台やキッチンカウンターなどは指輪を置き忘れがちになる場所です。なるべく日常的に身に着けることで紛失リスクを軽減できます。
外した時の保管場所を決めておく
なるべく指輪を外さないようにしていても、仕事中や家事などで外さなければいけない場面も出てきますよね。そういう時は、外した時の保管場所を決めておくのがおすすめです。保管場所は安全で目の届きやすい場所を選び、そこに毎回収納する習慣をつけるとよいでしょう。万が一なくした場合も、探す場所の目途が付きやすくなります。
外出時はジュエリーポーチや専用ケースを活用する
外出時に結婚指輪を外す可能性がある場合は、ジュエリーポーチや専用ケースを活用するのがおすすめ。
指輪を一時的にポケットにしまったり、台に置いたりすると、紛失のリスクが高まるだけでなく、傷や汚れが付いてしまう可能性もあります。柔らかな内装を備えたジュエリーポーチは、衝撃や摩擦から指輪を保護する役割もあり、手軽に持ち運びができます。持ち運び用のおしゃれなケースもたくさんあるので、気になる人は調べてみてくださいね。
サイズが緩くなったらメンテナンスに出す
なるべく指輪を外さないようにしていても、サイズが合わなければ日常のちょっとした動作で指輪が外れやすくなり、紛失するリスクが高まります。指輪のサイズが緩くなってきたなと感じたら早めにサイズ調整するようにしましょう。
結婚指輪が見つからなかったら
結婚指輪を紛失し、探しても見つからなかった場合には、「同じ結婚指輪を買い直す」もしくは「セカンドマリッジリングを購入する」ことを検討してみてはいかがでしょうか。
結婚指輪を購入してから数年以上経っていれば、ライフスタイルやお互いの好みが変わっていることもありますよね。この機会に結婚指輪を買い直すことで、今の自分にぴったり合う指輪を身に着けることができます。
同じ結婚指輪を買い直す
結婚当初に選び、愛用していたブランドで再購入すれば、新婚時代の思い出を再び形に残すことができます。失くしてしまった結婚指輪に対して愛着を強く抱いている場合、この方法を選ぶことで、大切な指輪を無くしてしまった後のショックな気持ちを和らげる効果も期待できます。
セカンドマリッジリングを検討する
結婚10周年、20周年など節目となるタイミングで購入することが多い「セカンドマリッジリング」。
結婚指輪をなくしてもすぐに買い直さず、節目となるタイミングでセカンドマリッジリングとして指輪を新調するのもおすすめです。
ふたりの絆を深めるきっかけにしよう!
結婚指輪をなくしてしまったら
①まずは、落ち着いて心当たりがある場所を探す
②警察や交番に「遺失物届」を提出する
③購入ブランドや店舗へ保証内容の問い合わせをする
④パートナーに報告
結婚指輪をなくさないために日頃からできること
①なるべく結婚指輪を外さない
②保管場所を決めておく
③外出時に外す場合はジュエリーポーチを使う
④サイズが緩くなったらメンテナンスに出す
※万が一、なくしてしまった時のために、指輪の特徴がわかる写真を残しておくのも◎
結婚指輪をなくしてしまうことはとてもショックな出来事ですよね。なかなか気持ちを切り替えるのも難しいと思います。しかし、場合によっては夫婦の絆を深めるきっかけにもなり得ます。
日常生活の中で、結婚指輪を保管する際のルールを決め、万一のためにすぐ対応できるように遺失物届についての基礎知識を持つことを心掛けましょう。